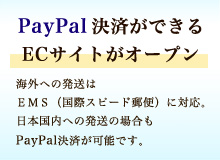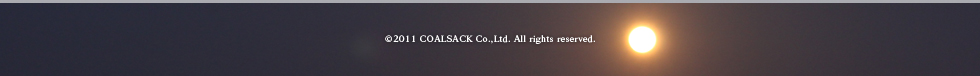青柳 俊哉 (あおやぎ としや)
<経歴>
1957年、福岡市生まれ、福岡市在住。「衣の会」同人、「コールサック」に寄稿。詩集『結晶』『球体の秋』。
<詩作品>
古代の朝
新緑のかぐわしい古代の朝に ひっそりと雨がふっている 所々に薄い緑の光がさしている 人間が生まれる前の黒い土が 柔らかくほぐされ 雨を吸っている 美しく整えられた黒い畝と緑草の中を少女のピンクの傘がひらいて舞って行く 空から落ちる水滴を 黒い土が吸いこむ 薄い緑の光がさして ぬれた緑草が輝きだす この古代の情感を 人間が生まれる前の神性を 人間の子が温かく彩りながら 霊歌を奏でる
球体の秋
ある秋の夕刻 光と影の境界が消えて 陰影のない無重力の球体が生まれ 日没前の空間を密かにつつみこんでゆく 遠い扇状の山々は円やかに屈曲してまぢかに迫り上がり 薄い斜光の射す里にひぐらしの声は衰え 虫の音に混じって彼岸花の花茎が赤く染まってくる
むかいのマンションの屋上では 地上から高く跳ね上がったボールが白い球体の貯水槽に重なって静止し そのまま一体となる 地上でボール遊びをしていた父子が白いボールを引き剝がそうとして球体を空へ持ち上げている 球体はしだいに宙へ浮かび上がり 父子も球体を持ち上げる姿勢のまま空へ上ってゆく 空の上ではカーンカーンと金属を打ち鳴らすような不思議な音が響きだす 球体は空高く上ってゆき その光景を見ていたマンションの住人たちも 窓からバルコニーから 昇天するように空へ上ってゆく
その夜 月光天は満月で 精霊たちは鐘を打ち鳴らして祝福し 滴るような金色の単を身に纏う女たちが 秋の糧を 満ち満ちて閉じてゆく球体の秋を 金色に発酵する月の滴で満たすのである
永 遠
1
詩稿を読んでいる私のまえに 樹々の葉影がゆれている そのゆらめく影の中に なにかをじっとみつめる私の碑が立っている ぬうぼうとしたのっぺらぼうの黒い石の影 その内部に ほろんでゆくものがあるとしても 激しい不安におびえる魂があるとしても その黒い象徴はそれらをのみこみ この時空に深く突き刺さっている
この永遠の石の棘 その石の周りを蝶のように影がゆらめいて そのゆらめく影の一秒一秒が 石の内部の私には鋭くひびきわたる生の永遠であった 私の上半身は真冬の温かい昼の陽射しの中にある
2
私の枕もとに 二歳に満たない女の児が眠っている 小さな両手を胸もとに愛らしくそろえて 安心しきって眠っている その幸福な寝顔が 成長し過ぎ去ってゆくこの子の生の 二度と訪れることのない瞬間を刻んでゆく この児の寝顔を美しくみながら 私は幸福をかみしめ その永遠の瞬間を心に刻み この児の人生が苦しみにみちたものでないことを願うのである